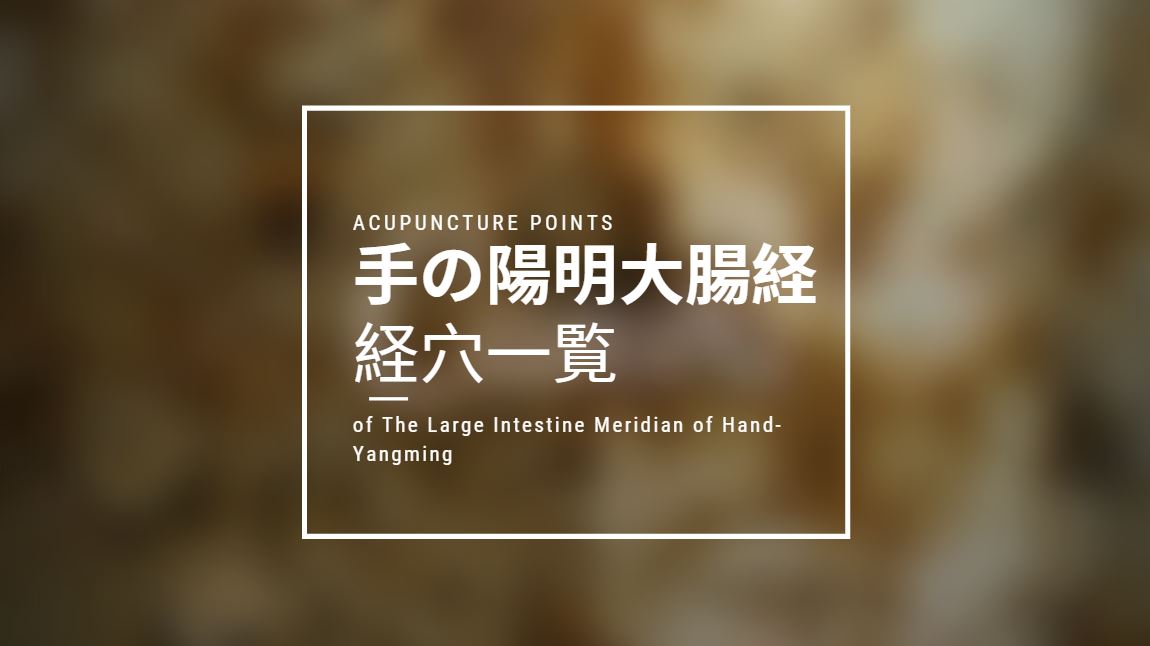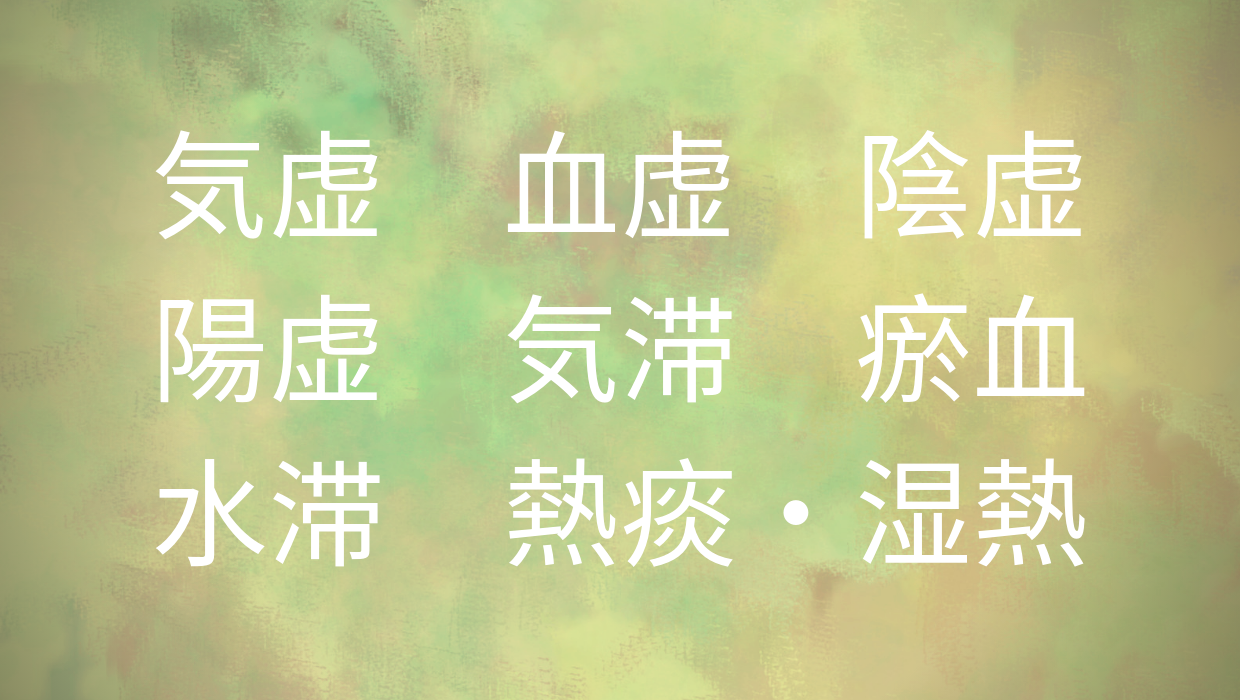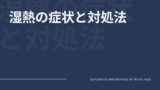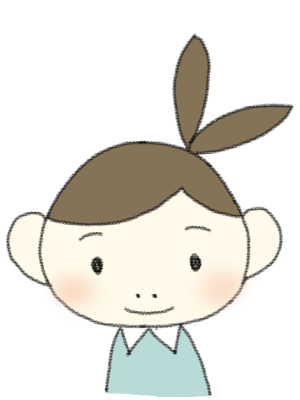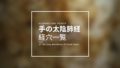手の陽明大腸経の経穴一覧です。ひとまず8つの証に効果のある経穴について、効能と場所をまとめてみました。
現在公開している項目は以下の通りです(2020/1/29時点)
※内容は順次追記していきます。
手の陽明大腸経とは
陽明の手陽経で、大腸とのつながりが深い。20の経穴を持ち、下痢や便秘、五十肩の治療などに有効。
手の陽明大腸経、英語名はLarge Intestine Meridianといい、略してLIと表記する。
LI1 商陽(しょうよう)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 別名:絶陽(ぜつよう)
- 要穴:大腸経の井金穴
- 穴性:泄熱消腫、開竅醒神
穴性解説
- 泄熱(せいねつ):熱を体外に出すこと
- 開竅(かいきょう):九竅(目、耳、鼻、口、尿道、肛門)の通りを良くすること
- 醒神(せいしん):意識をはっきりさせること
LI2 二間(じかん)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 別名:間谷(かんこく)
- 要穴:大腸経の栄水穴
- 穴性:散風、清熱、消腫
穴性解説
- 散風(さんふう):風の邪気を体外に出すこと
LI3 三間(さんかん)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 別名:少谷(しょうこく)
- 要穴:大腸経の兪木穴
- 穴性:散風、清熱、行気
穴性解説
- 行気(こうき):気の流れを良くすること。気滞を改善する
LI4 合谷(ごうこく)
合谷(ごうこく)は手の陽明大腸経に属する4番目の経穴。谷のような大きなくぼみであるという意味。別名の虎口は、手を横から見た時の形状が虎の横顔に似ていると例えたもの。
- 経絡:手の陽明大腸経
- 別名:虎口(ここう)
- 要穴:大腸の原穴、四総穴
合谷の効能
合谷は鎮静効果が高く、即効性があることから応急処置にも使われる特効ツボ。頭痛や耳鳴り、歯の痛みなど特に首から上の痛みによく効く。肩こりや胃痛などにも有効。自律神経にも作用するため精神安定などリラックス効果も。
- 穴性:鎮痛安神、神経活絡、疏風解表
穴性解説
- 疏風(そふう):風の邪気を分散させること
- 解表(げひょう):疏表ともいう。外感初期に体表の邪気を取り除くこと
合谷の場所
手の甲側の、人差し指と親指の骨がぶつかるくぼみ。人差し指側の骨のキワ。左右同様。
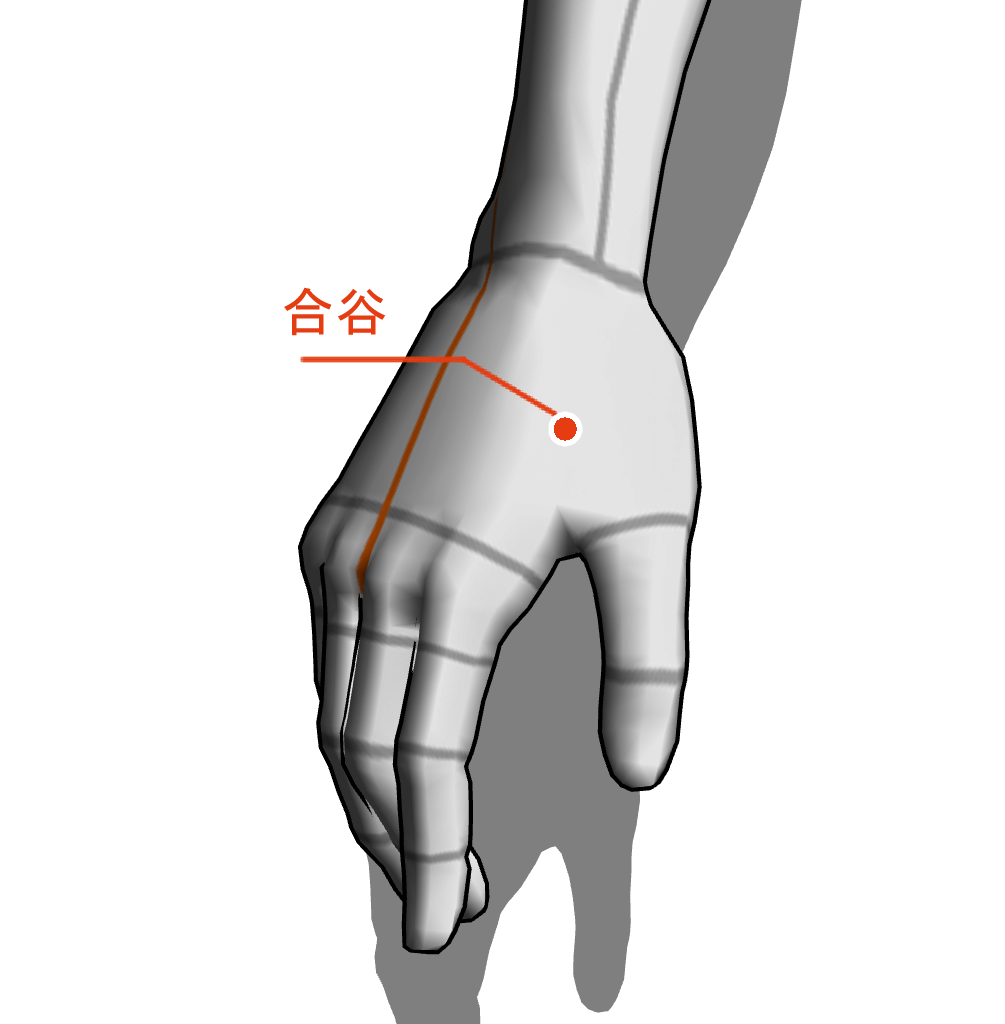
指の腹をツボに当て、人差し指の骨のキワに引っ掛けるようにして押し上げる。
LI5 陽渓(ようけい)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 別名:中魁(ちゅうかい)
- 要穴:大腸経の経火穴
- 穴性:清熱散風、明日利咽
穴性解説
- 散風(さんふう):風の邪気を体外に排出すること
- 利咽(りいん):のど(咽喉)の調子を整えること
LI6 偏歴(へんれき)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 要穴:大腸経の絡穴
- 穴性:清熱疏肺、通調水道
穴性解説
- 通調水道(つうちょうすいどう):水分代謝を促進すること
LI7 温溜(おんる)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 別名:逆注(ぎゃくちゅう)、蛇頭(じゃとう)、池頭(ちとう)
- 要穴:大腸経の郄穴
- 穴性:清熱解毒、調理腸胃
穴性解説
- 通調水道(つうちょうすいどう):水分代謝を促進すること
LI8 下廉(げれん)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 穴性:通腑気、利関節
穴性解説
- 通腑気(つうふき):大腸の働きを助け便通をよくすること
LI9 上廉(じょうれん)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 穴性:通腑気、利関節
穴性解説
- 通腑気(つうふき):大腸の働きを助け便通をよくすること
LI10 手三里(てさんり)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 別名:鬼邪(きじゃ)、三里(さんり)
- 穴性:去風通絡、調理腸胃、消腫止痛
LI11 曲池(きょくち)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 別名:鬼臣(きこ)
- 要穴:大腸経の合土穴
- 穴性:去風解表、清熱利湿、調和気血
LI12 肘髎(ちゅうりょう)
- 穴性:疏筋利節
穴性解説
- 疏筋利節(そきんりせつ):筋肉をほぐし関節の動きをなめらかにすること
LI13 手五里(てごり)
- 穴性:疏筋止痛、行気散瘀
穴性解説
- 疏筋(そきん):筋肉をほぐすこと
- 行気(こうき):気の流れをよくすること
- 散瘀(さんお):血の流れをよくすること。瘀血の改善に効果的
LI14 臂臑(ひじゅ)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 別名:頭衝(ずしょう)
- 穴性:去風通絡、清熱明目
穴性解説
- 清熱(せいねつ):体内の熱を冷ますこと
LI15 肩髃(けんぐう)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 穴性:疏風活絡、通利関節、調和気血
LI16 巨骨(ここつ)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 穴性:舒筋利筋
穴性解説
- 舒筋(じょきん):筋肉の動きを伸びやかにすること
LI17 天鼎(てんてい)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 穴性:理気化痰、清咽利膈
穴性解説
- 清咽(せいいん):のど(咽喉)の通りをよくすること
LI18 扶突(ふとつ)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 穴性:宣理肺気、利咽喉
LI19 禾髎(かりょう)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 穴性:去風開竅
LI20 迎香(げいこう)
- 経絡:手の陽明大腸経
- 別名:衝陽(しょうよう)
- 穴性:散風清熱、宣通鼻竅
穴性解説
- 鼻竅(びきょう):鼻の孔のこと