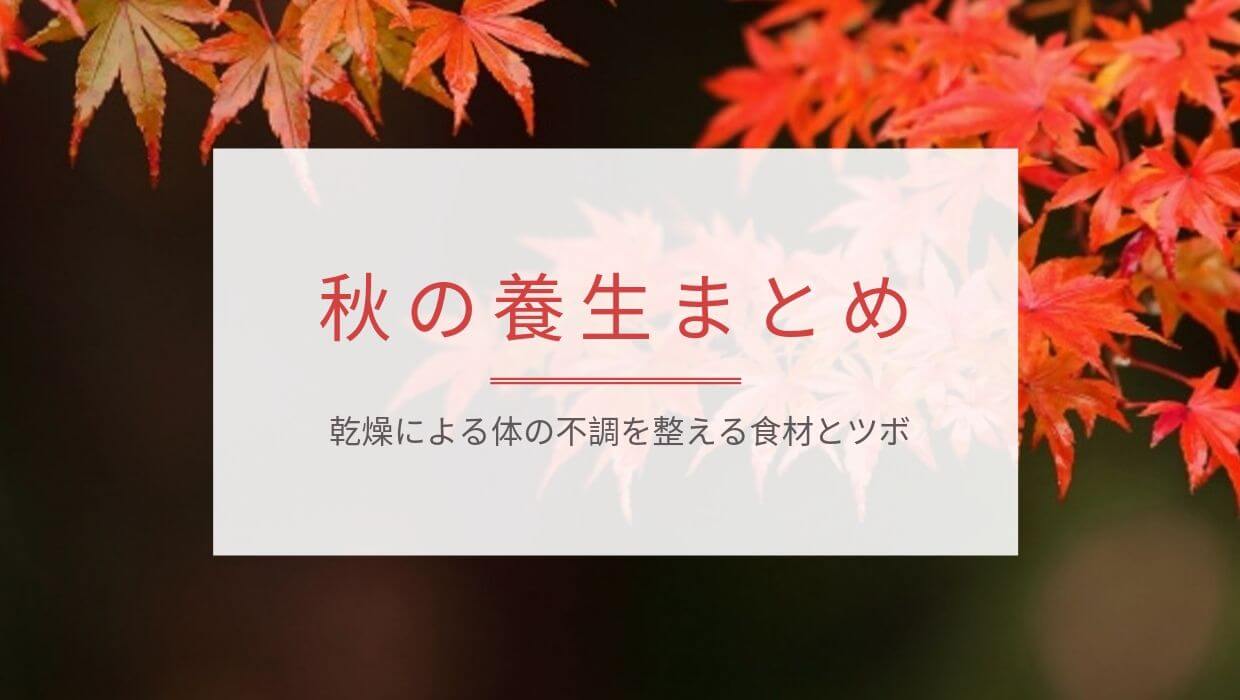秋は暑さも落ち着き一年の中でも過ごしやすい季節。ただし、気温差や乾燥によって体調を崩しやすい時期でもあります。
秋を健康的に過ごすためには、とにかく保湿!身体を潤す食材を積極的に取り入れることがポイントです。
このページでは、秋の時期に起こりがちな身体の不調とその対応策を、中医学や薬膳の観点からまとめています。
秋という季節の特徴

- 陽気が弱まり陰気が強くなる
秋を二十四節気に分けると、立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降まで6つの節気があります。陽気が次第に弱まり陰気が強くなってくる「陽消陰長」の時期です。
- 涼しくなり空気が乾燥しはじめる時期
五行説では、秋は「金」に属します。気候は涼しくなって過ごしやすくなりますが、日中の寒暖差で体調を崩したり、空気の乾燥による咳などの不調が出てくることもあります。
『黄帝内経 素問』より
秋は「容平」
万物が成熟し、容(かたち)が平定する。陽気が下がり始め、万物はその色を変えていく。
秋にいたわりたい臓腑
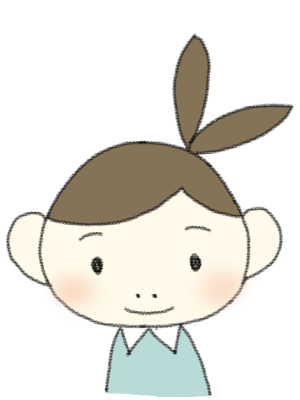
肺!
肺の働きは主に3つあります。
- 呼吸作用:きれいな空気(清気)を吸って汚れた空気(濁気)を吐き出す
- 宣発作用:気や津液を全身にいきわたらせる
- 粛降作用:気や津液を上から下へ降ろす
- 宣発(せんぱつ):上や外の方向へ拡散する
- 粛降(しゅくこう):下方向へ降ろす
- 衛気(えき):気の一種で防衛機能を持つ
宣発作用と粛降作用は二つで一つ。互いに関連しあっており、一方が異常を起こすともう一方も不調をきたします。
肺は呼吸をすることで外気を体内に取り込みます。そのため冷気や乾燥など体外環境の影響を受けやすい臓器です。
秋に起こりやすい症状

秋は五行において「金」に属します。収穫の季節で実り多い秋は、暑さが落ち着いて過ごしやすくなる時期。食欲が増す行楽シーズンでもありますが、燥邪(そうじゃ)によって肺がダメージを受けやすくなります。
- 燥邪(そうじゃ):乾燥の強い邪気で、口や鼻、皮膚の乾燥を引き起こす。秋から冬に注意が必要。
肺機能が低下すると、さまざまな不調が出てきます。
- 気道粘膜の乾燥⇒空咳や喘息など呼吸器系の不調
- 肺と関連のある鼻や皮膚、大腸への影響⇒鼻づまり、肌の乾燥、便秘
- 津液の巡りが滞る⇒痰、むくみ
- 衛気の不足⇒防衛機能が低下し風邪をひきやすくなる
代表的な症状は以下の通りです。
- 咳
- ぜんそく
- 鼻づまり
- 肌の乾燥、かゆみ
- 風邪
- 便秘
- むくみ
これらの不調を防ぐためには肺を潤し乾燥のダメージから守る養生をすることが大切です。
秋を元気に乗り切るために
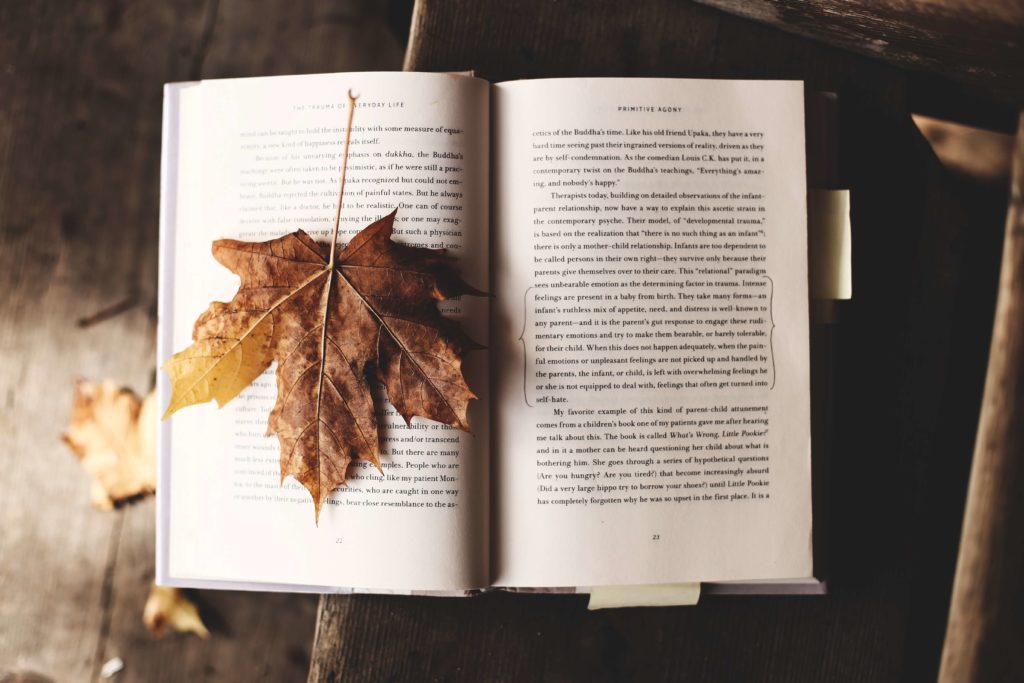
秋の養生のポイント
秋は特に乾燥に注意が必要です。初秋は「温燥」、中秋以降は「涼燥」といいます。温燥の時期は甘味や苦味のある食べ物を、涼燥の時期は温性で辛味や酸味のある食べ物を意識的にとるとよいでしょう。
- 早寝早起きを心がける
- 乾燥に注意し、特に肺を潤す食べ物をとる
- 冷えに注意する、ただし気温差があるため急に厚着しすぎないこと
- 外に向けていた意識を少しずつ内に収めるようにする
秋は厳しい冬を迎えるための準備をする期間ともいえます。夏の暑さで消耗した体力を取り戻し、免疫力を高めることが大切です。
秋の養生に役立つ食材
秋は空気の乾燥によって津液が不足しがちになるので、体内の陰気を養い肺を潤す食材を摂取するのがポイント。
■滋陰潤燥:陰液を滋養し、乾燥を防ぐ
豆腐、牛乳、きゅうり、れんこんなど
■滋陰温肺:津液を補い、肺を温める
生姜、ネギ、黒ゴマ、もち米、はちみつ、くるみなど
■滋陰潤肺:陰液を滋養し、肺を潤す
山芋、鶏卵、豚肉、貝類、カニなど
■益胃生津:胃を補益し、津液を生じさせる
米、じゃがいも、キャベツ、椎茸、鶏肉、牛肉など
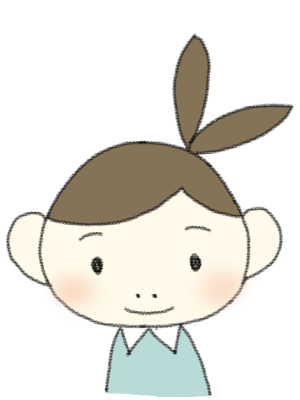
とにかく潤いが大事!
秋にオススメのツボ
- 肺兪:呼吸器疾患、乾燥を改善
- 扶突(ふとつ):のどの痛みを緩和
- 天突(てんとつ):のどのイガイガ
- 三陰交:陰液不足の便秘
- 陰陵泉:水分代謝アップで乾燥を改善
- 肩髃(けんぐう):皮膚のかゆみを和らげる
- 大巨(だいこ):腸の機能を高め便通を改善
秋にオススメの中国茶
秋は烏龍茶がおすすめです。烏龍茶は温性ですが発酵度の幅が広く、緑茶のようにスッキリ爽やかなものから紅茶のように濃厚で華やかなものまで味わいもさまざま。
その日の天気や気分によって飲み分けることができる烏龍茶は、 夏の暑さから冬の寒さへ天候の変化が大きい秋の時期にぴったりの中国茶です。